■報告削減の意義
第1章では、報告を減らす事で得られる時間的(金銭的)/心理的な価値を書いてきました。
自分自身の経験を振り返ると、報告を減らした後、沢山の方から
「**さんが、報告を削減する活動をやってくれたお陰で
今までよりも色んな報告が減り、凄く仕事が楽になった。ありがとう!」
と嬉しいメッセージが届きました。
時間的/心理的と書いてきましたが、報告を削減していくにあたって
推進者が報われるのは、何よりこうした言葉かなぁと思いました。
私自身、報告を減らす活動をする中で
「本当に自分の主張が正しいのかな?」
と疑心暗鬼になった場面もあり、自分がやってきた事が間違ってなかったんだと
実感が持てた瞬間でした。
特に大企業では、決裁スピードよりも、時間を掛けてでも正確に判断し
リスクを下げる事の方が重きを置かれる文化になりやすいと感じました。
今までの報告をやめたときには
「なんでこんな非効率なやり方をしていたんだろう?」
と思う事もありました。
報告を減らすまでは凄く大変ですが
減らしてみた後は案外気にならなくなるものです。
家にある不用物を捨てたり
処分するときの感覚と近いものがあると思います。
報告が減る事で、資料を作成する時間も減ります。
実はこっちの方が効果が大きいと思います。
資料を作成する上で、様々な効率化ツールがDXの促進に伴い
身近になってきましたが、まずはそもそもその資料を作る場面を減らすという
観点が必要だと思います。
■最後に
注意点として、報告を減らす=コミュニケーションを減らす
になってはいけないという事です。
上位者に対して、必要な情報が入らなくなるというのは、企業として健全な運営になりません。
必要な情報が速やかに入ってくる状態を保ちつつ
必要最小限の会議/報告の回数設定に留めるというのがポイントです。
次の第2章からは、報告を減らしていく上で
「報告を減らせない心理的・組織的な壁」 について
より実践的な内容を書いていきます。
💡この記事は連載「報告の省き方」シリーズの第1部です
次の記事:第2部「なぜ「報告をやめる」は反対されるのか?」
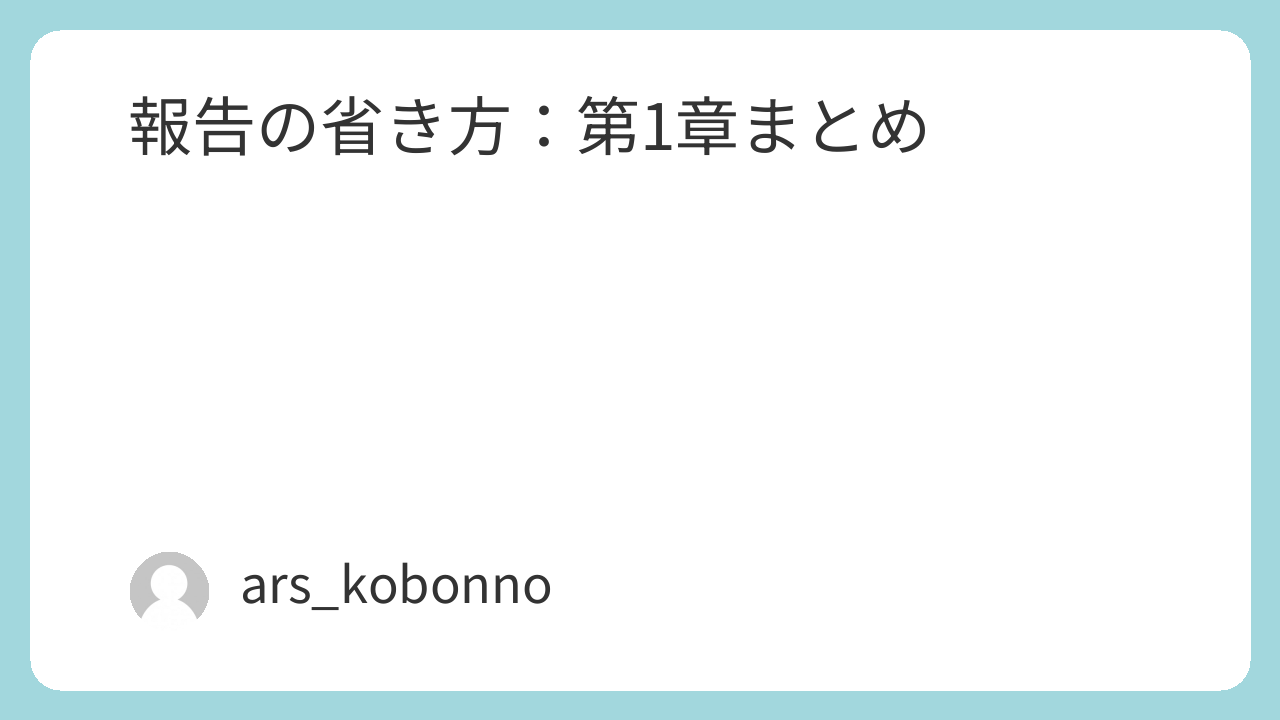
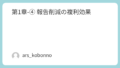
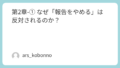
コメント